昭和20(1945)年5月。東京大空襲を経験したその夏、18歳の私は、工場が休みの日に一人で静岡県の三島から箱根へと越える荒れた山道を上っていた。空は抜けるように青く、緑の山々は鮮やかで、眼下には丹那トンネルの入口が見えた。
そのとき、米軍の戦闘機(グラマン)が頭上を飛びこえ、トンネルに向かって爆弾を発射した。轟然たる音とともに石塊が飛び散り、灰色の煙が立ちのぼった。私は恐怖で草むらに転げこんだ。
しかし同時に、それは自分とはまるで関係のない映画を見ているような、どこか別の世界の出来事のようだった。何が起こったというのか。私はそんな気持ちの自分を、実に変な感じで捉えていた。自分の身体が傷ついて激痛を感じなければ戦争はないに等しいかといえば、そうではない。戦争は身体を損なうか否かを問わず、若い心を情性の欠けた物に化していた。ちなみに、翌日の新聞もラジオもこの事について一言一句も触れていなかった。敗戦の日はもう近かった。
さて、今日の社会はどうなろうとしているだろうか。テレビやスマートフォンのヴァーチャルの世界に埋没した人々にとって、現実世界は関係ないかのようだ。だが、こうした人々には、70年前の私と同様に、スマホが現実なのではなくて、現実がスマホなのだ。
すべてが管理された社会は、明らかに機械的である。スーパーで買い物をして、レジで「袋は要らない」と言うのに袋で包む。タクシーに乗って「○○駅ではなく北○○駅へ」と2度も言うのに○○駅へ連れて行かれる。つまり人々は他人の言葉を聞く耳をもたない。したがって自分の言葉もない。機械の歯車になりきっていれば常に同じ言動で、それ以外のことはできないし、やろうともしない。現実が機械になった今、間もなく現実は彼らに、そして私に、人間としての呼吸を許さぬその真の姿をはっきり焼きつけてくるだろう。 この社会と歴史の中で、いったいどう生きたらよいのだろうか。まずは、眼を開いて周りを見ることだ。他人の言葉をできるだけしっかり受け止めることだ。そして、同時に自分自身の奥底から聞こえてくる、ひそやかな言葉に耳を傾けていくことだ。
結局、生きていることを体験しているのは自分であって、マスコミの示す社会一般ではない。自分は誰であり、どう行為することが自分なのか。自己の深淵から聞こえてくる声に耳を傾けて、今日の一日を生きるしかない。
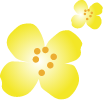
1952年、東京文理科大学心理学科卒業。法務技官として少年鑑別所勤務の後、国学院大学文学部教授、筑波大学心理学系教授、文教大学人間科学部教授を経て、現在、筑波大学名誉教授。主著『心理劇と分裂病患者』(星和書店、1984年)、『集団臨床心理学の視点』(誠信書房、1991 年)、『新訂 ロールプレイング』(日本文化科学社、2003年)ほか多数。2011年より、カウンセリングオフィス・ヒロ顧問。







